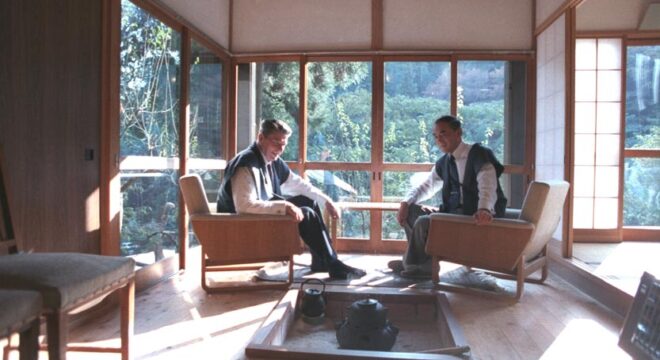2025年度の予算が、まもなく成立の見込みです。少数与党の下の予算審議は、衆議院での減額修正、そして参議院での再修正など、審議が始まった時点では予測できない事態の連続でした。改めて、修正後の予算を点検すると、
(1)所得税の最低非課税額は160万円になり、夫婦それぞれ400万円の年収で4万円程度減税になり、
(2)今年度から公立高校授業料の無償化についての所得制限が撤廃され、来年度からは私立高校の授業料の無償化についても所得制限がなくなり
(3)3人以上の多子世帯の大学授業料無償化の所得制限の廃止
(4)高額医療費の負担増加は先送りになりました。
こうした修正はパートの主婦やアルバイトの学生、子育て中の方々などにとっては福音ですが、いま国民が直面している物価高に対する対策にはほとんど手が付けられていません。立憲民主党などが主張していたガソリンの暫定税率の廃止については、石破総理は「暫定税率廃止は決まっている。
ただ何時からということは財源の関係で言えない」と国会で答弁しています。これでは生活者にとっては「絵にかいた餅」です。しかも、石破総理自身が、まだ参議院で予算を審議している最中に、「直ちに物価対策を策定すべき」と言い出す始末ですから、「それなら、今審議している予算は何なのか!」と野党が怒るのはもっともです。残念ながら、予算が成立しても物価高に苦しむ人々の生活は楽にはなりません。
私は、今国会では古巣の財務金融委員会に所属しています。3月26日の委員会で日銀総裁に対して行った質疑で、はっきりしたのは、物価(特に食料品)がこれだけ高騰しているのに、日銀は「基調的物価は2%以下だ」として、利上げに対して慎重な見方を続けています。
私はやみくもに金利を上げろと言っているわけではありませんが、政治に対する忖度で利上げのタイミングを間違えれば、円安が進行し、物価の上昇を抑えきれなくなって結果的に人々の暮らしに打撃を与えます。
食料品の高騰については、決して一過性のものではないと考え、食料品の値上がりから庶民を守るには、やはり消費税の食料品の税率を最低でも5%程度に下げるべきだと考えています。私は35年前の消費税の導入時から、消費税は高齢化社会の社会保障費を賄うためには必要だと思ってきました。
しかし、最近の食料品価格の高騰とエンゲル係数やジニ係数上昇に見られる社会格差の拡大を考えると、消費税が当初から持っていた逆進性を緩和するために食料品の税率をさらに下げるべきだと考えるようになりました。また、これまで、消費税の逆進性の緩和のため「給付付き税額控除」の制度をつくるべきだと主張してきました。
先の定額減税の給付金の手続きの混乱などをみて、還付を公平、敏速に行うには、まだしばらく時間がかかると感じ、当面、軽減税率を採用するしかないと考えています。私が、最初に「給付付き税額控除」の制度を考えたのは、カナダの付加価値税の制度を勉強してのことでしたが、カナダやアメリカでは小切手で給付を行うのが通常になっています。もちろん、アメリカは消費税のような付加価値税は連邦政府にはありません。
消費税の食料品の税率を下げることによって消費税収の減少分は、所得「1億円の壁」と言われる1億円以上の高所得者の金融所得の課税を強化するなど、税制が本来持つ、所得の再分配機能を回復させることを通して、税収を確保できます。私の、考えに対するご意見をぜひ聞かせてください。