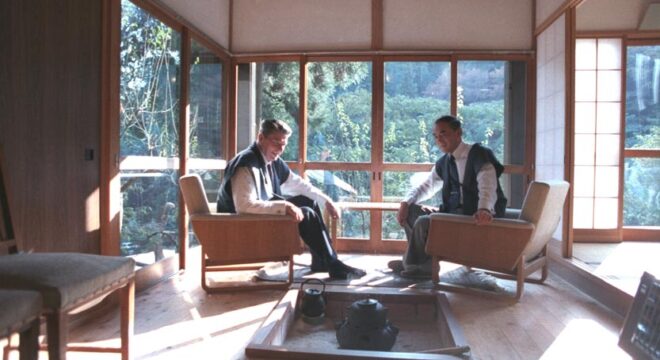立憲民主党は4月25日の代表会見で、物価高対策として食料品の消費税をゼロにすることを発表しました。この決定に対して、4月27日付の朝日新聞社説では「減税公約の重みと疑問」と題し、「そもそもいま消費税の減税が必要な情勢なのか。
物価の先行きは不透明だが、エネルギー価格の高騰は落ち着きつつあり、賃上げが広がる」と、立憲民主党が掲げた「食料品の消費税ゼロ」政策を批判しています。このほかにも立憲民主党の本部には同じように消費税の減税に対して疑問を呈する意見が多く寄せられている事実があります。
言うまでもなく今回の立憲民主党の消費税減税は、消費税全体の減税ではなく「食料品の税率をゼロ」です。私は、本ダイアリーの3月28日号で「食料品の軽減税率を5%程度に下げること」を提言しています。
今回の立憲民主党が決定した食料品の消費税率をゼロにする政策は、党内の数次にわたる議論で決まったことですから私は賛成です。
そもそも私が食料品の消費税率の引き下げを提案した最大の理由は、最近の物価高の中で庶民がコメをはじめとした食料品の高騰に悲鳴を上げている現状があるからです。
週末にスーパーに買い物に行くと、食料品売り場の前で、買おうかどうか財布と相談しながら考え込んでいる消費者の姿を見ることが多くなりました。総務省の「家計調査」でも、2023年の日本のエンゲル係数(家計費に占める食費の割合)が28%に上昇しています。
OECDの調べでは、2022年のアメリカのエンゲル係数は16%、ドイツは19%です。この数字からも日本人は確実に貧しくなっていて、特に賃上げとは無縁で年金額が少ないお年寄りの買い物姿は見るに忍びません。
もう一つ、日本の消費税の根本的な欠陥は、他国の付加価値税に比べて食料品の税率が高いことです。イギリスは消費税の標準税率は20%ですが、食料品はゼロ税率、カナダも同様に食料品はゼロ税率、ドイツは標準税率19%に対して食料品などの軽減税率は7%です。フィリピン、タイ、韓国などアジアで消費税を導入している国々では食料品は「非課税」です。
いずれの国も食料品はゼロ税率か非課税になっていて、庶民の生活に対する配慮が施されています。なお、「ゼロ税率」と「非課税」の違いは、消費者の税負担が無いことは同じでも、ゼロ税率では流通過程で支払った消費税額が「仕入れ控除」できることです。このためゼロ税率は事業者に負担がかかりません。
ただし、食料品のゼロ税率の問題は、高所得層や富裕層が購入する高額食品も税負担が小さくなってしまうことです。その点は無視してもいいとの考えもありますが、「応能負担」の原則からも、また税収の落ち込みをできるだけ少なくするためには、高所得者には高い税金を払ってもらうことも必要です。
そこでカナダなどで実施されているのが、低所得者に消費税の一部を還付する「給付付き税額控除」の制度です。立憲民主党の前身である民主党は結党直後の1990年代に「給付付き税額控除」を行っているカナダに調査団を派遣しました。
カナダでは小切手を使って政府からの給付金を個人に支払っていますが、小切手が一般的でないわが国では、個人のマイナンバーと所得額が紐付けられていなければ、正確な給付ができません。今後、この問題を解決するために、これまでのコロナ給付金などの経験も踏まえながら、どんな方法があるか早急に検討する必要があります。