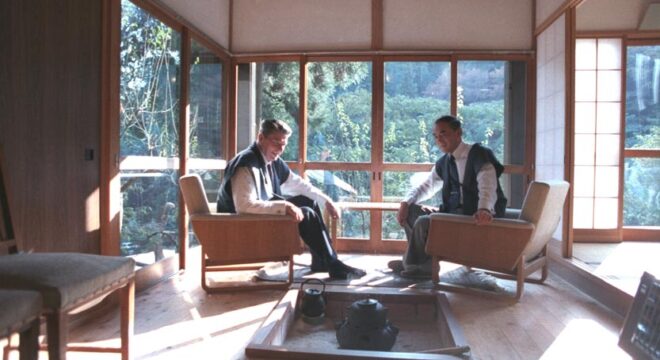今年は日本の敗戦から80年の節目の年で同時に、国際連合(国連)が誕生してから80年の記念すべき年です。日本の外交は国連中心主義と教科書などでは教えていますが、実際、国連誕生の歴史についてはあまり知られていないのではないでしょうか。
国連の誕生日は1945年10月24日と言われ、この日を国連デーとして日本でも渋谷区にある国連大学を中心に各種の催しがおこなわれます。
日本の終戦は8月15日とされていますが、正式にはミズリー号上で降伏文書に調印したのは9月2日ですから、日本の降伏により第二次世界大戦が終結してから、わずか50日余りで51か国が加入した国連が正式発足するとはずいぶん手際がいいというのが学校の社会科で国連について学んだときの私の正直な感想です。
しかし、実際には日本とドイツが降伏前の1945年4月、両国に宣戦布告している50か国がサンフランシスコで会議を開き、国連憲章に調印をしています。ここから国連は実質的にスタートしたと言ってもいいでしょう。国連憲章の内容については前年の8月から10月にかけてワシントンで開かれた米国、英国、ソ連、中華民国の4者で原案が作成されていました。10月24日は、こうした下準備がすべて整った上で、国連が正式発足した日です。
第一次世界大戦後の国際連盟では米国が参加を見送り、その結果、第二次世界大戦を防げなかった歴史的事実は多くの人が知るところでしょう。現在の国連は米国が中心になって第二次世界大戦後の国際秩序を定めた組織ですが、第二次トランプ政権は、国連と距離を置くことに熱心です。
2025年10月からの会計年度の予算で、国連関係の金額を33・3億ドル(約4780億円)削減することを決めています。また、2月4日には、国連人権理事会からの離脱、ユネスコの参加を見直す大統領令に署名しています。第一次世界大戦後の国際連盟への米国の無関心さが再び思いだされます。
米国が国連に背を向けるのと対称的に、最近目立つのが中国の国連への関心の高さです。中国が主張する「人類運命共同体」の目標は、現代における国連憲章の反映であるとの見解を中国は幾度となく明らかにしています。
現在、日本にとって国連改革の最大の問題は言うまでもなく、常任理事国入りです。この問題について、国連自身2004年に安保理の改革についてハイレベル委員会を設置し、具体案として、常任理事国を6か国、非常任理事国を3か国増やして、安保理理事国を24か国とする案を提出しています。
残念ながらこの案は、中国と韓国の反対により2005年9月の国連総会では採択に至りませんでした。
中国が本気で、国連重視の姿勢をとるなら、安保理の常任理事国の改革は避けて通れない課題だと思います。現在の日本と中国の政府間の関係は決して良好なものとは言えませんが、この際、中国に対して、国連改革を一緒にやろうと呼びかけることも必要だと思います。
また韓国の新大統領は、米国訪問に先立って来日し、未来志向の関係を築くことを確認しましたから、韓国にもこの問題での協力を働きかけることも重要です。
国連誕生80年を契機に、日本が国連の中で存在感を示すチャンスを活用しない手はありません。米国抜きの国連を放置すると、世界は再び戦火にまみれることを心配します。