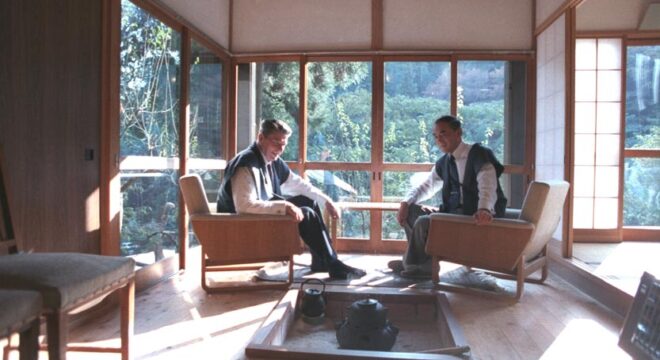自動車や鉄鋼などに対する米国の追加関税は、今年7月の日米合意、9月の文書署名を経て決着しました。自動車への関税が27.5%から15%へ引き下げられ、従来の関税率が15%以上の品目には新たな上乗せがないことも盛り込まれるなど一定の成果が得られたと評価する声もあります。
日米貿易協定については2019年に国会で承認されています。当時の政府答弁は、「自動車や関連部品について関税を撤廃する。そこに向けて両国政府で話し合う」というものでした。しかし現実には追加関税が課せられ、政府答弁と矛盾する事態に陥っています。
2019年当時もトランプ大統領と合意したわけですから、今回の交渉は日米貿易協定の違反である可能性が大きいにもかかわらず日本政府は国会で「整合性について重大な懸念を持っている」と答弁するにとどまり、「日米貿易協定違反だ」と最後の最後まで断言できなかったことは、スタート時から米国の言いなりの交渉であった証しです。
今回の決着をうけて国内経済に対する影響緩和のための対策もあらためて万全にしていかねばなりません。早期かつ正確な情報提供、中小零細企業の資金繰り支援は、国会でも政府の前向きな答弁があったところであり、引き続き徹底を求めたいと思います。
関税実務の業務プロセスやオペレーションの課題にも向き合う必要があります。例えば食料品の缶詰がアルミ製である場合、誰が、どの国で精錬し、どの国で鋳造し、アルミ部分に限った重量がどのくらいで、ということを明らかにする作業や査定のやり直しが追加されることになります。
他にも中古エンジンの場合、中古であるため品目や材料など皆目見当がつけられず書類に記入できなくなる事態も起こり得ます。税率が決着してもなお、具体的な企業実務は手探り状態になると想定されます。これに対して正確な情報提供のみならず、企業に寄り添った支援を行うことが必要です。
関税コストを誰が負うかとの問題も残されています。一般的には輸入側である米国現地企業が関税を負担しますが、貿易量が減ってしまうから輸出側である日本企業に負担を強要し、値引きを要求されることも予測されます。
こうした価格転嫁については、国内の取引では、企業規模や業界ごとに下請Gメン、トラックGメン、建設Gメン等々が配置されておりますが、輸出入に関する価格転嫁を見張る人はいません。経産省が米国通商代表部(USTR)に働きかけるなどして、適切な価格転嫁のための枠組みを作ることが有効です。
誰が総理になっても一日も早く、国会を召集してこれらの課題に対応すべきです。